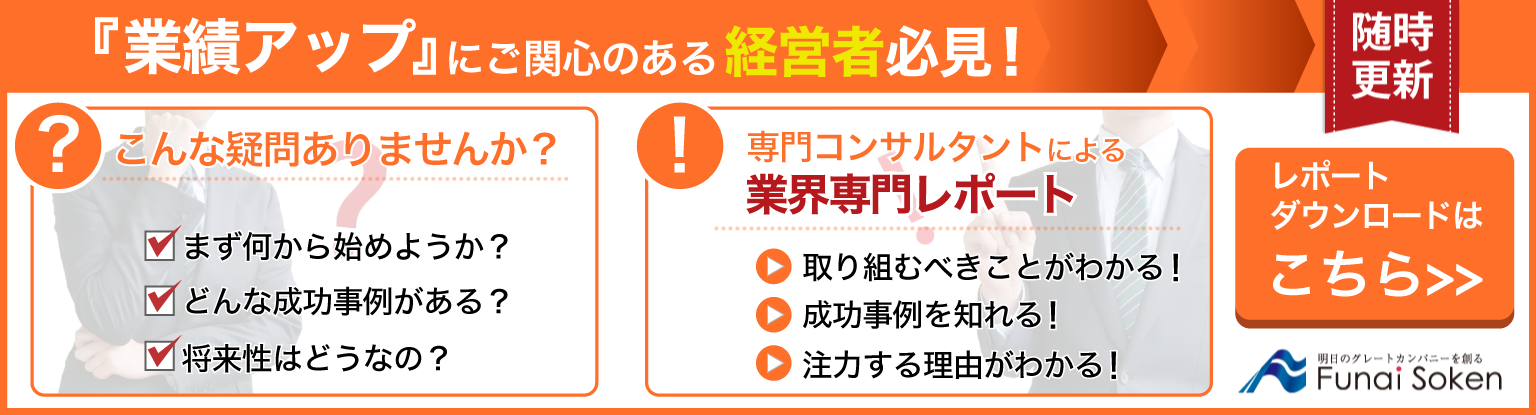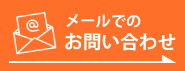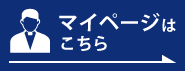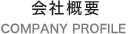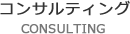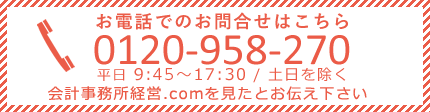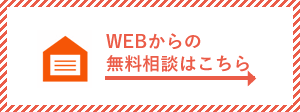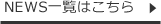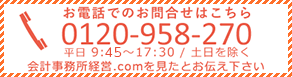税理士の将来性、その【理由】を知っていますか?事務所の将来を左右する業界動向を徹底解説
目次
はじめに:2025年以降、税理士業界は本当に変わるのか?
「AIに仕事が奪われる」という言葉を聞いて、ご自身の事務所の将来に不安を感じている税理士の先生も多いのではないでしょうか。特に2025年が目前に迫り、税理士業界の今後の動向がどうなるのか、業界全体が大きな変化の岐路に立たされていることは事実です。税理士の仕事は本当になくなってしまうのでしょうか。
なぜ今、税理士の「将来性」に不安の声が多いのか?
税理士の将来性に不安の声が多い理由は、主に3つあります。第一に、AIやクラウド会計ソフトの急速な普及による業務の自動化です。第二に、日本の中小企業の減少という市場の構造的な問題です。第三に、税理士登録者の高齢化と若手の減少という業界内部の課題です。これらの理由が複合的に絡み合い、税理士の今後に対する漠然とした不安を生み出しています。
本記事の概要:事務所経営者が「今」知るべき業界の現状と今後の対策
本記事では、税理士の今後の将来性について、業界の現状と課題を徹底的に分析します。AIによって代替される可能性が高い業務と、逆に人間の税理士だからこそ価値が高まる業務を明確に区別します。さらに、今後の税理士に求められる専門分野やスキル、会計事務所が生き残るための具体的な対策(IT活用、マーケティング、採用戦略など)を詳しく解説します。この記事を読むことで、税理士の今後に対する不安を解消し、事務所の将来に向けた経営方針を考えるヒントを得ることができます。会計事務所の経営者の方、勤務税理士の方、これから税理士を目指す方に、ぜひ読んでいただきたい内容です。
1. 税理士の今後に影響するAI・クラウドソフトの普及と業務自動化
税理士の今後を語る上で、AIやクラウド会計ソフトの普及は避けて通れないテーマです。近年の技術革新は目覚ましく、かつては税理士や事務所スタッフが多くの時間を費やしていた業務が、自動化されつつあります。例えば、freeeやマネーフォワードといったクラウド会計ソフトは、銀行口座やクレジットカードと連携し、仕訳の入力を自動で行うようになりました。AI-OCRの進化により、紙の領収書や請求書の読み取り精度も飛躍的に向上しています。この自動化の流れは、2025年以降さらに加速することが予想され、税理士の業務内容に大きな影響を与えることは確実です。
記帳代行など、AIに代替される税理士の今後の業務
税理士の業務の中で、AIに代替される可能性が高いのは、記帳代行や仕訳入力といったルーティン業務です。これらの業務は、データの入力や転記が主体であり、ルールが明確であるため、AIやソフトが得意とする分野です。私もコンサルティングの現場で、ある会計事務所がクラウド会計ソフトを積極的に導入し、記帳代行に要する業務工数を約8割削減した事例を見てきました。その事務所は、空いた時間を顧客への経営アドバイスに充てることで、顧問料の向上に成功しています。税理士の今後は、こうした単純作業から脱却し、より付加価値の高いサービスへシフトすることが求められます。単純な申告書作成も、ソフトの進化によって自動化が進んでいくでしょう。税理士の今後の仕事は、AIが作成した申告書のレビューや、より難しい税務相談へと移行していく必要があります。
2. 税理士の今後に立ちはだかる中小企業の減少と顧客ニーズの変化
税理士の今後の将来性を考える上で、AIの技術的な問題と並んで深刻なのが、市場環境の変化です。税理士の主たる顧客である中小企業の数は、日本の人口減少や経営者の高齢化に伴い、年々減少傾向にあります。中小企業庁のデータによれば、企業の休廃業・解散件数は高止まりしており、市場規模そのものが縮小している現状があります。これは、税理士にとって顧問契約の獲得競争が激化することを意味します。税理士の今後は、減っていくパイを奪い合うのではなく、顧客のニーズの変化に対応し、新たなサービスを提供していくことが重要です。
市場規模の縮小と税理士の今後に求められる経営コンサルティング
顧客である中小企業の数が減っている一方で、生き残りをかけて事業を営む経営者の悩みは複雑化しています。経営者が税理士に求めるニーズは、かつてのような「税金計算の代行」から、「経営全般の相談相手」へと大きく変化しています。税務・会計の知識をベースにした、財務コンサルティングや経営コンサルティングへの期待が非常に高まっています。例えば、資金調達の支援、補助金・助成金の提案、事業計画の策定サポートなどです。税理士の今後は、税務申告という過去の結果を処理する業務に留まらず、顧客の将来の経営をサポートするアドバイザーとしての役割が強く求められています。
3. 税理士の今後に影を落とす業界の構造的な問題
税理士の今後の課題は、AIや市場といった外部環境だけではありません。税理士の業界内部にも、構造的な問題が存在します。その一つが、税理士登録者の高齢化です。日本税理士会連合会のデータ(2023年版など)を見ると、税理士の年齢構成は年々高まっており、60歳以上の割合が約半数を占めるという状況です。高齢化が進むこと自体が問題なのではなく、ITへの対応の遅れや、事務所の事業承継が進んでいない点が課題となっています。税理士の今後の業界のためには、若手の活躍が不可欠です。
登録者数の高齢化と税理士の今後に必要な若手合格者の減少
高齢化が進む一方で、税理士の今後を担う若手の合格者は減少傾向にあります。税理士試験の受験者数は、ピーク時と比較して大幅に減っており、資格取得の難易度や勉強時間の長さが、若手人材の業界への参入障壁となっている可能性があります。会計事務所の経営者からは、採用が難しいという声も多く聞かれます。私の知る税理士法人では、税理士試験の科目合格者を積極的に採用し、事務所内で学習をサポートする体制を構築することで、若手の確保と育成に成功しています。税理士の今後の業界の将来性を担保するためには、働きながら勉強を続けられる環境整備や、資格の魅力を向上させる対策が必要です。2023年の税制改正で受験資格が緩和された点は、今後の受験者増加に期待が持てる変化です。
4. AI時代でも安泰!税理士の今後に残る「人間にしかできない業務」
ここまで税理士の今後に対する不安要素を解説してきましたが、AIが普及するからこそ、人間の税理士の価値が高まる業務分野も多く存在します。AIはデータ処理や計算は得意ですが、相手の感情を汲み取ったり、複雑な状況を総合的に判断したりすることはできません。税理士の今後の仕事は、こうした「人間にしかできない」業務へとシフトしていきます。経営者の悩みに寄り添い、専門家としての知識と経験に基づいたアドバイスを行うことの重要性は、今後ますます高まるでしょう。
複雑な税務相談や税理士の今後に必須のアドバイス業務
AIに代替できない筆頭は、複雑な税務相談や個別の経営アドバイスです。例えば、相続案件における遺産分割の提案です。以前、私が支援したある税理士の先生は、AIによる相続税シミュレーションを活用しつつも、最終的な分割方法は、ご家族それぞれの関係性や感情を丁寧にヒアリングした上で提案していました。ご家族が納得できる提案は、データだけでは実現できず、税理士の先生の「人間力」こそが成功の理由でした。税理士の今後は、まさにここにあります。税務調査の対応における折衝力や、組織再編、事業承継といった個別性の高いコンサルティングは、AIには難しい、税理士の今後の中核的な業務となっていきます。
5. 税理士の今後を拓く!会計事務所に不可欠なIT活用術
税理士の今後において、AIは「仕事を奪われる相手」ではなく、「業務を効率化し、価値を高めるツール」として活用する必要があります。会計事務所のIT活用は、今後の将来性を左右する極めて重要な経営課題です。ITを活用することで、記帳代行などの単純作業から解放され、経営者へのアドバイスという付加価値の高い業務に時間を割くことができます。ITの導入を進める方針は、税理士の今後の事務所経営において必須です。
業務効率化と税理士の今後に向けた高付加価値サービス
税理士の今後に必要なIT活用の目的は、業務効率化と高付加価値サービスの提供という2点です。業務効率化の面では、クラウド会計ソフトの導入はもちろん、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)による定型作業の自動化や、CRM(顧客関係管理)ツールによる顧客情報の一元管理などが考えられます。効率化によって生み出された時間は、高付加価値サービスの提供に充てるべきです。例えば、クラウド会計ソフトでリアルタイムにデータを分析し、顧客の財務状況についてタイムリーなアドバイスを行うことができます。税理士の今後は、ITを活用して顧客のDX(デジタル・トランスフォーメーション)を支援するアドバイザーとしての役割も期待されています。
6. 税理士の今後に需要が増える専門分野:事業承継・M&A支援
税理士の今後の将来性は、どの分野に専門性を持つかで大きく変わります。今後需要が増えると予想される専門分野の一つが、事業承継・M&A支援です。先にも触れた通り、中小企業の経営者の高齢化は深刻な問題であり、今後10年で多くの中小企業が事業承継の時期を迎えます。しかし、後継者不足に悩む企業は少なくありません。税理士は、顧問先企業の経営状況や財務状況を最も詳しく把握している存在であり、事業承継の相談相手として最適です。
中小企業庁のデータに見る税理士の今後の可能性
中小企業庁が発表しているデータによれば、後継者不在の中小企業は全国に数十万社存在すると言われています。この市場は、税理士の今後にとって非常に大きなビジネスチャンスです。事業承継は、相続税や贈与税といった税務の知識はもちろん、法人の組織再編、M&Aのノウハウ、財務分析など、高い専門性が求められます。経営者の個人資産と会社の資産を一体で考える必要があり、税理士の専門性が最も活かせる分野の一つです。税理士の今後は、事業承継の専門家として、顧客の事業と想いを次の時代に繋ぐ重要な役割を担うことができます。
7. 税理士の今後に需要が増える専門分野:国際税務
税理士の今後に需要が増える専門分野として、国際税務も挙げられます。企業のグローバル化は、大企業だけの話ではなくなりました。中小企業や個人事業主であっても、インターネットを活用して海外と取引を行うことは一般的です。また、海外に子会社を設立したり、逆に外資系企業が日本に進出してきたりするケースも増加しています。こうしたグローバル化の流れに伴い、国際税務の知識を持つ税理士への需要は急速に高まっています。
グローバル化と税理士の今後の需要
国際税務は、日本の税制だけでなく、租税条約や移転価格税制など、非常に難しいかつ専門的な知識が必要とされる領域です。英語などの語学力が求められるケースも多く、対応できる税理士の数はまだ多くありません。それだけに、国際税務に対応できる税理士は、今後の将来性が非常に高いと言えます。私の知る税理士は、国際税務に特化し、越境ECを行うクライアント向けのサービスを提供することで、他の事務所との差別化に成功しています。税理士の今後は、こうしたニッチでも需要の高い分野で専門性を高めることが生き残りの鍵となります。
8. 税理士の今後に需要が増える専門分野:経営・財務コンサルティングとDX支援
税理士の今後の需要として、最も中核となるのが経営・財務コンサルティングとDX支援です。AIが普及しても、経営者の悩みがなくなるわけではありません。むしろ、変化の激しい時代だからこそ、経営者は信頼できるアドバイザーを求めています。税理士は、会社の「数字」という客観的なデータを把握している唯一の士業であり、経営者の一番身近な相談相手となる可能性を秘めています。
資金調達・補助金申請と税理士の今後のサポート
経営・財務コンサルティングの具体例として、資金調達の支援や補助金・助成金の申請サポートがあります。中小企業にとって、資金調達は経営の生命線です。税理士が経営計画や事業計画の策定を支援し、金融機関との橋渡しを行うことで、顧客の経営を強力にサポートできます。また、国や自治体は多くの補助金制度を設けていますが、情報が複雑で申請書類の作成も難しく、活用できていない企業が多いのが現状です。税理士がこれらの情報を提供し、申請をサポートすることは、顧客にとって非常に高い価値を提供します。税理士の今後は、税務の専門家であると同時に、経営のアドバイザーとしての役割を積極的に担っていくことが重要です。
9. 税理士の今後に向けた事務所の専門性・強みの構築方法
税理士の今後の時代では、どの事務所も同じサービスを提供していては生き残りが難しくなります。AIによる自動化が進む中で、事務所としての専門性や強みを明確に構築することが不可欠です。「何でもやります」という総合型の事務所ではなく、「この分野ならA事務所」と経営者から選ばれる存在を目指す必要があります。専門性を構築することは、税理士の今後の経営戦略の中核です。
特化分野の選択と税理士の今後を支えるデジタルマーケティング
専門性・強みを構築するには、まず特化分野を選択することがはじめの一歩です。先に紹介した事業承継、国際税務、経営コンサルティングのほか、相続、不動産、IT業種特化、医療業種特化など、様々な切り口が考えられます。自社の強みや経験、市場のニーズを分析し、どの分野で勝負していくかを決めることが大切です。そして、専門性を構築したら、それを顧客に知ってもらう必要があります。税理士の今後の顧客獲得は、デジタルマーケティングが重要です。専門分野に関するコラム記事をサイトで発信したり、SNSを活用したり、オンラインセミナーを開催するなど、積極的な情報発信が顧問契約の獲得に繋がります。
10. 税理士の今後を担う!活躍できる人材の採用と育成
税理士の今後の事務所経営において、専門性を構築し高付加価値サービスを提供するためには、「人」の問題、すなわち人材の採用と育成が極めて重要です。AIを活用し、コンサルティングを行うのは人間です。事務所の方針に合った優秀な人材を採用し、活躍できる環境を整えることが、税理士の今後の将来性を左右します。若手の税理士試験受験者が減少している中、採用戦略は事務所の課題です。
多様な人材と税理士の今後に向けたキャリアプラン
税理士の今後の会計事務所に必要なのは、税務・会計の知識を持つ人材だけではありません。ITに強い人材、マーケティングが得意な人材、コンサルティング経験者、公認会計士など、多様なスキルを持つ人材を採用し、組織を構築していく必要があります。私の知るある税理士法人は、公認会計士やITコンサルタント経験者を積極的に採用し、コンサルティング部門を新設しました。税理士の今後を見据えた組織づくりが成功し、税務顧問以外の収益の柱が育っています。また、採用した人材が長く活躍できるよう、明確なキャリアプランを提示することも大切です。若手が勉強と仕事を両立できる体制や、コンサルティングなどの新しいスキルを学ぶ機会を提供することが、税理士の今後の事務所の強みとなります。
11. 税理士の今後に活かす成功事例!顧問契約に繋がる情報発信
税理士の今後の専門性を構築し(第9章)、人材を採用・育成したら(第10章)、次はそれを活用していかにして顧問契約に繋げていくかが課題となります。税理士の今後は、待っているだけでは顧客は増えません。事務所の専門性を活かした積極的な情報発信が、見込み顧客との接点を生み出します。成功事例に学ぶ、効果的な情報発信の方法を紹介します。
無料相談・セミナーと税理士の今後に繋がるコンテンツ活用
顧問契約に繋げる効果的な方法として、無料相談やセミナーの開催があります。例えば、「相続税対策セミナー」や「インボイス制度対策無料相談会」など、顧客の悩みや関心が高いテーマを設定します。セミナーや相談をオンラインで開催すれば、全国から見込み顧客にアクセスすることが可能です。税理士の今後は、デジタルを活用した営業活動が一般になっていくでしょう。また、自社のサイトに専門性の高いコラム記事を掲載するコンテンツマーケティングも有効です。役立つ情報を発信し続けることで、事務所の専門性が認知され、問い合わせに繋がります。税理士の今後は、こうした情報発信を通じて事務所の強みを見える化することが、成功のポイントです。
まとめ:税理士の今後はAI時代の変化をチャンスに変える経営方針で決まる
本記事では、税理士の今後の将来性について、AIの影響、市場の変化、業界の課題、そして今後の対策まで詳しく解説してきました。税理士の今後は、「AIに仕事を奪われる」といった悲観的なものではありません。むしろ、AIやITは、税理士を単純作業から解放し、より付加価値の高い仕事に集中させてくれるチャンスであると考えるべきです。税理士の今後の将来性は、事務所の経営方針と変化への対応力で決まると言えます。
これからの税理士業界で生き残るための重要ポイントと今後の展望
これからの税理士業界で活躍し続けるための重要なポイントは、大きく3つあります。第一に、AIやクラウドソフトを脅威ではなくツールとして積極的に活用し、業務の徹底的な効率化を進めることです。第二に、記帳代行や単純な申告書作成から脱却し、経営コンサルティング、事業承継支援、国際税務など、人間にしかできない高付加価値な専門分野を構築することです。第三に、多様な人材を採用・育成し、事務所の組織力を高め、デジタルマーケティングを活用して専門性を発信していくことです。税理士の今後の展望は、経営者のアドバイザーとして不可欠な存在になることで、開けていきます。
税理士の今後は、変化を恐れず新たな価値提供を目指すことが成功への道
税理士の今後に対する不安の多くは、変化の内容がわからないことに起因します。しかし、変化の方向性は明確です。税理士に求められる役割は、「代行業者」から「ビジネスパートナー」へと進化しています。税理士という資格の価値がなくなるわけではなく、税務・会計の専門知識をベースにした新たな価値提供が求められているのです。税理士の今後の成功は、変化を恐れず、顧客である経営者のニーズに応え、新たなサービスを提供しようと挑戦し続けるかどうかにかかっています。本記事が、あなたの事務所の今後の方針を検討する一助となれば幸いです。