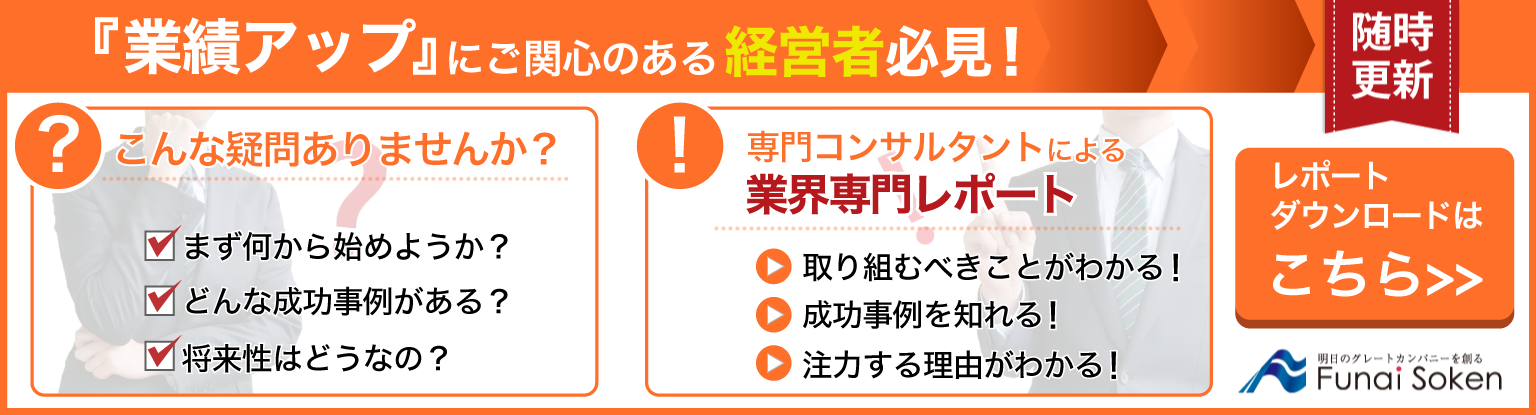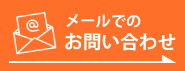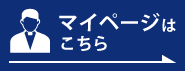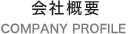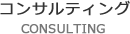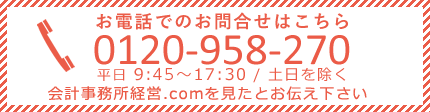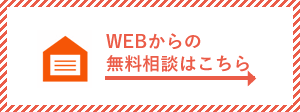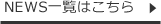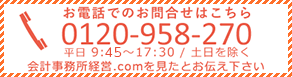【2025年会計事務所M&A最新時流】
お世話になっております。
船井総研あがたFASの山中です。
聞きなれない社名かと思いますが、本年1月より船井総研内でM&Aを専門に扱う子会社として「船井総研あがたFAS」を設立し、M&A仲介及びFA業務を取り扱う専門会社を設立しました。
私もそちらに異動となり、会計事務所専門のM&Aを担当させていただいております。
会計事務所の皆様とは事務所のM&Aだけでなく、顧問先のM&Aも含めた連携をさせていただければと思います。
目次
2025年以降、会計事務所のM&Aは間違いなく増加する
会計事務所の皆様にとっては「M&A」というワード自体はよく聞くお話しかと思います。
顧問先のM&Aのご相談や日本M&Aセンターとの協力関係は古くから多くの事務所が取り組んできたことと思います。
M&A仲介会社からの営業などを通じて、皆様自身も中小企業M&Aが全国的に増加している、というのは肌でお感じなのではないでしょうか?
実際にM&Aの件数は毎年増加しています。
そのような時流の中、会計事務所のM&Aも増加を続けており、私たちのもとにいただくご相談も目に見えて増えてきています。
ご相談いただくのは、
・代表自身のご年齢による退任
・後継者不在
・承継予定の税理士の経営能力の不安
・事務所マネジメントの課題
・職員の採用不能、離職に伴う人員不足
こうした理由を背景としたM&A選択肢の可能性です。
実際に会計事務所ではこれまでもM&Aに積極的に取り組む事務所があり、
グループ経営も含めて多種多様な形でM&Aが行われてきました。
実際に経験された方の中には、「成功とは言えなかった」という方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、中にはM&Aをしながらも離脱は全くなく、M&Aをきっかけとした職員の離職がほとんどない、という事務所もあります。
会計事務所の成功と失敗を分けるポイントとは何か?
実際の事例を通じてお伝えさせていただきたいと思います。
会計事務所のM&A 成功と失敗を分けるポイントとは
皆様、「MIKATAグループ」はご存じでしょうか?
過去20件以上のM&Aを実施して多くの会計事務所との統合を続けており、成長を続けている税理士法人を中心としたグループです。
これまでM&A後の解消は1件もなく、またM&Aをきっかけとして職員の離脱もほとんどない、理想的なM&Aを実現されています。
なぜそのようなことが可能なのか?
どうしたらそれだけのM&Aの相談を集めることができるのか?
何のためにそれだけのM&Aを進めているのか?
承継した事務所は本当にうまくいっているのか?
承継に際してどのくらいのお金が動いているのか?
また、どうやって支払っているのか?
など、話を聞けば聞くほど疑問がどんどん出てきます。
更には社内で顧問先のM&A仲介を担当する部署もあり、M&A増加の時流に合わせて事務所の成長を続けられています。
代表の柴田先生に色々とお伺いさせていただく中で、多くのポイントがあることはお伺いしましたが、
1点だけM&Aの成功と失敗を分けるであろうポイントは、「無理して変えないこと」です。
会計事務所には組織の文化だけでなく、会計ソフトや業務方針、細かなルールなど事務所によって多くの違いがあります。
M&Aを機にそうしたルールを統合していくということを考えることが多いのですが、急激な変化はハレーションを引き起こし
職員の離職や求心力の低下を招きかねません。
そこで、経理や申告等の重要な点を除いて「変えない」ことがポイントであるとお伺いしました。
でも、「変えない」のであればなぜわざわざM&Aをするのか?
どうやって経営統合していくのか?
ますます疑問が深まるのですが・・・。
そこで、今回MIKATAグループ代表 柴田先生に直接お話をお伺いし、MIKATAグループが取り組むM&Aの戦略をお話いただくセミナーを開催させていただくこととなりました。
オンライン 無料 秘密厳守のセミナーです。
会計事務所のM&Aの本音を知りたい、という方は是非ともご参加いただきたいと思います。